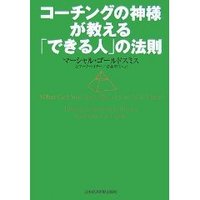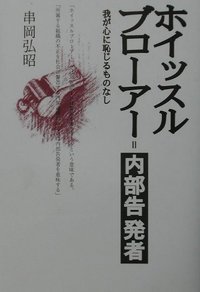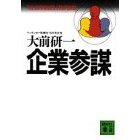2008年09月28日
「くるみん」
みなさん、こんにちは、佐野です。
「少子高齢化」の問題は、既に企業経営に影響を与え始めています。
各社、早めにこの「問題」に対し、取り組みが必要です。
「少子高齢化」の問題は、既に企業経営に影響を与え始めています。
各社、早めにこの「問題」に対し、取り組みが必要です。
これは、真剣に「ヘビー」な問題です。
「少子高齢化」が、日本の「人口構造」を知らないうちに、かつ確実に、大きく変えようとしています。
生産年齢人口(15-64歳)は、1995年をピークに減り続けています。
生産年齢人口が「減る」ということは、企業にとっては「労働者と消費者が同時に減り続けていく」ことを意味します。
今日は、「労働者が減り続ける」現実に、どう対応すべきか、考えましょう。
そして、それを考えるキーワードが、今日のタイトル「くるみん」なのです。
労働力を確保するために、「女性に長く働いてもらえる」職場を確保することは、もはや「マスト」(必須)です。
2003年制定の「次世代育成支援対策推進法」(「次世代法」ともいいます)に基づき、企業における社員の子育て支援対策への取り組みも活発化しています。
この「くるみん」は、「次世代育成支援認定マーク」と呼ばれ、
企業が、従業員の子育て支援のために行動計画を策定し、実施し、一定の基準を満たせば、厚生労働大臣により認定される仕組みです。
いわば、「くるみん」が付与されていたら、その企業は、子育て支援に積極的な企業だとアピールできます。
最近の採用面接では、応募学生が、「くるみん」取得の有無を確認する時代になっています。
認定企業は、2008年 6月末時点で、全国 545社(300人以下企業 47社含む)を数えます。
日本は、「女性活用」という点で遅れています。
一人目の子供を産んで、「7割の女性」が「退職」してしまう現実。
あるいは、「役職別管理職に占める女性の割合」は、
USA 42.5%
ドイツ 37.3%
UK 35%
そして、日本は、「10.1%」。
貴社は、何%ですか?
「働きたい女性を、どこまで受けられる度量があるか。」
経営者として、真剣に意識しなくてはならないテーマです。
「少子高齢化」が、日本の「人口構造」を知らないうちに、かつ確実に、大きく変えようとしています。
生産年齢人口(15-64歳)は、1995年をピークに減り続けています。
生産年齢人口が「減る」ということは、企業にとっては「労働者と消費者が同時に減り続けていく」ことを意味します。
今日は、「労働者が減り続ける」現実に、どう対応すべきか、考えましょう。
そして、それを考えるキーワードが、今日のタイトル「くるみん」なのです。
労働力を確保するために、「女性に長く働いてもらえる」職場を確保することは、もはや「マスト」(必須)です。
2003年制定の「次世代育成支援対策推進法」(「次世代法」ともいいます)に基づき、企業における社員の子育て支援対策への取り組みも活発化しています。
この「くるみん」は、「次世代育成支援認定マーク」と呼ばれ、
企業が、従業員の子育て支援のために行動計画を策定し、実施し、一定の基準を満たせば、厚生労働大臣により認定される仕組みです。
いわば、「くるみん」が付与されていたら、その企業は、子育て支援に積極的な企業だとアピールできます。
最近の採用面接では、応募学生が、「くるみん」取得の有無を確認する時代になっています。
認定企業は、2008年 6月末時点で、全国 545社(300人以下企業 47社含む)を数えます。
日本は、「女性活用」という点で遅れています。
一人目の子供を産んで、「7割の女性」が「退職」してしまう現実。
あるいは、「役職別管理職に占める女性の割合」は、
USA 42.5%
ドイツ 37.3%
UK 35%
そして、日本は、「10.1%」。
貴社は、何%ですか?
「働きたい女性を、どこまで受けられる度量があるか。」
経営者として、真剣に意識しなくてはならないテーマです。
Posted by トッティ at 23:50│Comments(0)
│企業経営